今月の書評2発目はポール・ブルームの『反共感論』について。先月発売されていたのを書店にて偶然発見。そろそろ恋愛道場で『共感』をテーマに書こうと思っていたので、キャッチーなタイトルに惹かれてふと手に取ってみた。著者のことは存じ上げなかったが、興味を惹かれたのは帯でスティーブ・ピンカーが称賛していたのもある。ピンカーというのは歩く心理学辞典のような人で、しかも全方位からの反論やツッコミに完璧に対応しようとするのでいつも面白いほどマトモなことしか言わないという。というわけで本書も少なくともトンデモ本ではないとみた。サブタイトルは『社会はいかに判断を誤るか』になっているが、そこは華麗にスルーしたい。スルーの理由は至極明快で、社会全体の判断なんて知ったこっちゃないから。主語がデカいんだよ主語が。自分の関心は「個人がより良い生活を送っていくこと」にある。社会というのは個人の集積ではあるけれど、社会全体に関するアレコレは実際にその権限と責任をもつ立場にある人が考えて実行していくことであって、ぼく自身が携わる領域ではない。と思っている。ぼくはもともとはナンパ講師なので、徹底したミクロ目線が刷り込まれている。たとえば「世の中の秩序構築・維持」と「わたしやあなたの成長」を天秤にかけたら、自分は間違いなく後者に価値を見出すということ。もちろんこれは極端な例だし、あんまり大きな声では言えないけどね。
『反共感論』という逆張りのタイトルからも予想されるとおり、本書では『共感の弊害』がいろんな視点から網羅的に論じられている。1章の総論の後、2章と3章ではマクロ視点、つまり「人々が共感を軸にした意思決定をすることで世の中全体はどのようにBADになるのか」が論じられいる。(これが本書のコアの内容であるが、ここは前述のとおりスルー。どうしても興味がある方はここに http://gigazine.net/news/20160322-against-empathy/ ダイジェストの要約が動画付き掲載されているのでチェックしてみて)
その後4章、5章でようやく個人に焦点を当てたミクロ視点が登場し、共感があなた(共感する側)やわたし(共感される側)にとってもいかにBADであるかが述べられていく。著者は「丁寧に読んでもらえないと誤解を招くかもしれない」と前置きしながらも、この逆張りの主張を大胆に展開している。
ところで『共感』と聞いた時、あなたが思うことはなんだろうか。たとえばあなたは友人が彼女に振られて落ち込んでいるとき、彼を慰めているうちに自分もいつのまにか落ち込んでいたというようなというような経験をしたことはないだろうか?あるいは、落ち込みやすい恋人と長い間付きあっているうちに自分もいつのまにか精神的に落ち込みやすい体質になってきたというような経験はどうだろう?あるいは逆に、「ちょっとは人の気持ちも考えてよ!」と女から切れ気味に罵られて落ち込んだ経験はないだろうか?良かれと思って発した言葉が相手の気持ちを逆なでしてしまった経験はどうだろう?
あなたは共感する側であるとともに、共感される側でもある。自分が何かしらの悩みを抱えているときは誰かから共感してもらいたいと思ったことがあるだろうか?自分のことを何から何までわかってくれる人が一人でも傍にいてくれたら、生きていくことのすべてのモチベーションが湧いてくるのにと感じたこと、あるいは逆にこの人にだけは自分の苦しみなんてわかってたまるものかと息巻いたことは?こうやって振り返ってみると、われわれの身近な人間関係に「共感」は様々な形で関係していることがわかるはずだ。
余談だけど、毎日の中で感じるこういうモヤモヤは、まだ<問い>には昇華されていない。油断していると、モヤモヤは生活をしているうちに容易に過去に追いやられ、そして記憶の底に沈殿してすぐに忘れ去られてしまう。もしモヤモヤをうまく問いの形に昇華してしっかりと掴まえておくことができたなら、答えは自然と導きだされるだろう。たとえば誰かと出会った時にふと答えらしきものに出会えることもあるかもしれない。だが<問い>へと昇華されるには日々の熟成、つまり体験の積み重ねがどうしても必要になる。そして読書体験というのは、そういう体験の中でも特殊な形をしていて、何かしらの問いを見出すのに一役買ってくれることはとても多い。それは必ずしも著者が本の中で提示する問いと一致するとは限らない。むしろ本の趣旨とは関係なく勝手に問いが芽生えていくというほうが多いように思う。自分はいつもそういう目論見でもって本屋をぶらついては、めぼしい本を漁っている。
本書のフレームと主張
それはともかくまずは丁寧に本の内容を追ってみたい。著者はどういう趣旨でもって共感に反対しているのか。まずは本書を読み解いていくうえでの簡単な枠組みを説明したい。
著者はいろいろとごっちゃにされがちな『共感』を2つの側面に分類する。
ひとつ目は情動的共感。つまり相手が感じている感情を自分も同じ様に感じる能力のこと。それはたとえば、目の前に飢えたホームレスがいる時に相手の感じているように自分も感じること。いわゆる一般的な意味での共感(Empathy)である。
ふたつ目は認知的共感。他人が何を考えているのか?何がその人を怒らせたのか?彼は何を快く感じ何を苦痛に感じるのか?彼が感じている痛みは何なのか?そういったことを、必ずしも自分では経験せずに理解する能力のこと。そしてこの認知的共感を土台にして相手を気遣うことをCompassionという。日本語で言うところの「思いやり」である。
共感とは対照的に、思いやりは他者の苦しみの共有を意味しない。そうではなく、それは他者に対する温かさ、配慮、気づかい、そして他者の福祉を向上させようとする強い動機によって特徴づけられる。思いやりは他者に向けられた感情であり、他者とともに感じることではない(P.170)
ブルームの主張は明快で、彼は後者の認知的共感の方を高く評価する一方で、前者の情動的共感を否定する。苦しんでいる人を目の前にして自分も同じ様に苦しもうとする姿勢自体は尊いものかもしれない。だけどその姿勢はいろんな点で自分に害を及ぼすことのほうが多いし、他人にもあまり益をもたらさないよねと。以下もう少し詳しく論旨を架空の対話形式で要約してみよう。
ブルーム
「人は他者に共感しようとするとき苦しみを過剰に感じることがある。これは燃え尽き(burnout)と呼ばれていて、共感による苦痛が恒常的に経験されると健康にも悪影響が及び、心臓病や糖尿病、がんなどのもとになることも知られている」
ぼく
「燃え尽きのことはあなたに言われなくても充分知ってますよ。だけどあなたは逆に自分が苦しくて助けが欲しい立場に立った時、自分の気持ちを相手にわかってもらいたいと直観的に思うことはないのですか?」
ブルーム
「相手に共感を促すことにはリスクがある。私を助けてくれるはずの人が、私の痛みを感じて耐えがたく思い、歩み去ってしまったなどということにもなりかねない」
ぼく
「たとえそうであっても、どんなリスクを冒してでも自分の感情を相手と分かち合いたい。自分は孤独ではないと思いたい時というのはあるでしょう?」
ブルーム
「親密な関係の場合は相手に対して自然とそういう『共感してほしい』という気持ちも湧くだろう。親しい人が、自分がみじめなときに満足していたり、自分が満足しているときにみじめな様子をしていたりすれば、間違いなくろうばいするはずだ。しかし、それは決して私たちが共感を望んでいるからではない」
ぼく
「それではあなたは一体何を望んでいるんですか?」
ブルーム
「たいていの人は、愛され、理解され、気づかわれることを望んでいる。つまり誰かと親密な関係を形成することを望んでいるのだ。たしかに相手からの共感を得ると親密な関係を形成しやすくなるかもしれないが、共感を得ること自体は目的ではないはずだ。もし共感によってでなくても、本当に途切れないような親密な関係が築けるなら満足できるかもしれない」
ぼく
「あなたはとんだ大馬鹿ですね。関係性が大事?誰かがカウンセリングに足を運ぶのはカウンセラーと親密な関係になりたいからだとあなたは思ってるんですか!」
ブルーム
「医師やセラピストなどの治療者に一番求められているのは、患者の感情を適切に理解すること、そのうえで適切に処置することであって、患者の感情と自分の感情を同期させることではない」
ぼく
「他にも反論があります。自分がイライラしている時というのは、無関係な人を不用意に挑発して相手のこともイライラさせたくなりますよね。またもっと特殊な例を出すと、レイプの被害者が加害者に対して望むことは、謝罪でも賠償でもなく、『わたしが味わったこの苦痛や絶望をまったく同じようにおまえにも味わわせてやりたい』ですよ。被害者は加害者と親密な関係を結びたいとでも言うんですか。彼は自分ひとりが地獄にいることには耐えられないんだ。死なばもろとも。これこそわたしたちが他者に共感を求めている証拠じゃないですか」
ブルーム
「たしかにそれは否めない。被害者は、加害者が誠実な謝罪を行なうには、自分がいかなる悪事を行なったのかを理解していなければならないと、そしてそのためには加害者自身が同じ経験をする必要があると思っているはずだ」
ぼく
「誠実な謝罪なんて、、これっぽちの価値もあるもんですか」
ブルーム
「とはいえ共感を大切に思う気持ちはある程度は理解する。彼らの気持ちを代弁するとこうだ。他者の経験を真に理解する唯一の方法は、他者が感じていることを自分でも感じることではないのか?(P.181)」
ぼく
「そのとおりです」
ブルーム
「思うに、その種の反論をする人はまったく別の問題に気をとられているのではないだろうか。つまりそういう人は自分自身で経験しない限り何ごとも真に理解することはできないという考えに駆り立てられているのである。彼らは次のように考える。すぐれたセラピストは、抑うつ、不安、孤独とはどのようなものであるかを理解しているはずだ。そしてそれは、セラピスト自身が、少なくとも一度は抑うつ、不安、孤独を感じた経験があることを意味する。哲学者のローリー・ポールが『変容的な経験』と呼ぶこの種の経験を理解するためには、自分自身でそれを体験しておく必要がある。想像力だけでは十分ではない。ほんものの経験に代わるものなどないのである。とね」
ぼく
「・・・」
ブルーム
「自分は一体何様だと言うのかね。それにこれは、情動的共感を支持する根拠にはなっていない。その種の評価を行うのに、他者の感情を実際にミラーリングする必要などない。そもそも、あなたに話しかけている人の苦悩を、今は冷静であってもかつて自分でも経験したことがあるゆえに理解するのと、ミラーリングによってその苦悩をたった今感じることによって理解するのとでは、天と地ほどの違いがある。いかなる意味でも共感をともなわない前者の理解、つまり純然たる理解によって、後者の持つあらゆる恩恵が得られるとともに、後者にともなうコストを一切避けることができるのだ」
ぼく
「あなたのおっしゃることはおおむね理解しました。ただぼくたち人間は無意識の奴隷だという側面もある。『共感がよくない』という前提を受け入れるとしても、共感せずにはいられないということはあるのではないでしょうか」
ブルーム
「われわれは無意識の奴隷であると同時に、理性の生き物でもある。共感は単なる反射ではなく、養ったり、抑えたり、発達させたり、想像力で拡張させたりすることのできるものだ。さらに言えば、意志力によって焦点を絞ったり、導いたりすることもできる。アリストテレスの時代から、理性は人間の最高知性であるとされてきた。人間は理性的にこの問題を解決していくことができるとわたしは信じているよ」
読後の感想
著者の議論の流れは非常に明快で、その枠組みの中では何の疑問の余地も残らない。とはいえ、、ぼくとは決定的に話が嚙み合わない。同じ事柄について語っているとは思えないようなチグハグさがある。理屈は理解するが「はいそうですか、たしかに『情動的共感』はよくないですね」と切り捨てることができない。ぼくの感覚が「ストップ」を発している。というわけで取り上げておいてなんだが、個人的にはあまり刺さる本ではなかったことは正直に白状しておこう。
食い違いの原因はシンプルで、ぼくの掲げる問いと彼の掲げる問いが根本的に違ったということだ。ぼくは彼に対して「わたし/あなたのこの共感したい/されたい気持ちは何なのか?」と問い続け、彼は一貫して「共感の<是非>」について問うて論じているのである。2、3章はマクロ視点なので是か非かを論じるのもまだ納得できる。ただ個人レベルなると<是非>では動かない。動けない。たしかに共感をする/しないは意志の力でコントロールできるというのはその通りだと思う。自らの意志である程度は相手の感情(ひいてはその相手自身)から遠ざかることもできるし、反対に集中することもある程度はできる。しかし、その意志自体を働かせる際に裡なるモチベーションが介在しているのだ。「メリットが少なくてデメリットが多いから共感を減らそう」というようなモチベーションで意志をコントロールするのは難しい。表面的なメリットやデメリットはモチベーションとしては案外弱いのである。
ぼく自身は他人との間にいつもなんとも言えない<ズレ>や<食い違い>を感じていたので、相手に共感するのが難しいときが頻繁にあった。たとえば皆が盛り上がっているときに自分はどうしようもなく白けてしまったり、反対に自分ひとりだけ盛り上がってしまって相手を白けさせたりすることが多かった。相手の悩みがどうしようもなくくだらないものに感じられたり、自分の感じていることは相手からするとメンドクサイことだと思われることも多かった。周りの人たちの感じてることがなんとなくわからなくなって、時に彼らがとてつもなく愚鈍で醜悪な存在に思えたりもした。よくわからないものに出会うと人は崇拝し畏怖するか軽蔑して見下すかのどちらかであるという。たいがいの場合、ぼくは後者だったし、怒りや侮蔑が消えた後には苛立ちが残り、それらが消えた後も最後までずっと残る感覚が『疎外感』で、これはとても堪えた。
そういった背景があって、ぼくは「共感」つまり他人の感情を探求し始め、そしてその必然として自分の感情を探求し始めた(のだと今では分析している。)間違っても「共感するべきか否か」なんていう問題意識で取り組み始めたわけではない。共感のプロセスでは何度も「燃え尽き」を味わったし、自分がどうしようもなく堕ちて汚れてしまったような感覚も刻み込まれた。本書ではデメリットだとみなされるようなことをいくつも経てきたし、デメリットであるという自覚もあったがそれでストップがかかるようなことは起こらなかった。そのプロセスの中でぼくがどういう体験をしてどういう認識を獲得していったかについては、ここでは触れている余裕がないので割愛する。むしろそれは他人と共有するようなものではない、ひたすら個人的なものであると思う。「いろいろあったけどやってよかった!」というようなナイーブで前向きなフィードバックで片づけるものでもない。「自己成長のためにそういった探求プロセスを推奨するか?」ともし誰かに尋ねられたら、「特に推奨しない」と答えるだろうし、そもそも彼らはぼくの言葉などお構いなしに動くだろう。人間は是非の道理などでは動かない。裡なるモチベーションでのみ動く。
しかしその一方でブルームは「共感を絶対的に擁護する人々」いわゆる共感厨がどうしようもなく陥ってしまうこれらの「神経症的な罠」のことをしっかりと見抜いてもいる。そして「おいおい、そんなに思い詰めるなよ。それよりもいったん冷静になって自分がいったい何に囚われているのかをしっかりと見つめたほうがいいよ」と暗に諭してくれているようでもある。彼のアドバイスは圧倒的に正しい。まさに情動的共感ではなく認知的共感からくるCompassionに基づいたものだ。彼は本書で主張していたことをそのまま実践し読者にアドバイスしてくれていたのかもしれない。そしてそのようなアドバイスは神経症の人間にとってはそよ風のように微力なものでしかないということも、あるいは承知しているのかもしれない。と少し思った。
====
来月号のテーマは「共感とアプローチ」です。
ここでは一応是非の問題はクリアしたとみなして、理論パートでは『共感の技術』つまり方法論だけに的を絞って書いていくつもりです。他人とのコミュニケーションの悩みを人間関係の問題として捉えると泥沼にはまる。あの人はわたしのことが嫌いみたいだ。どうしよう、、みたいな。そうではなく、共感技術の問題として捉えるとどうなるか。つまり「共感には精度がある」と捉えるとどうなるか。
相手の感情に意識を向けるという感じをぼくなりに翻訳すると「近づく」という言葉が一番しっくりくる。それがブルームのいうところの「情動的共感」なのか「認知的共感」なのかは定かではない。共感をすると結果的にその相手との関係は親密になるかもしれないが、ぼくの中では「近づく」というのは、その場その時で起こる局所的な体験なのである。
自分では相手に近づいた気になっていても、共感の精度が低く実際は遠ざかっていることも多い。そういう齟齬があるときにコミュニケーションの問題は起こりやすい。またズカズカと無遠慮に踏み込んで近づいていっていいものでもない。心というのはどこまでも繊細で未知のものである。それに近づき触れる試み、その方法論について次号の本文では書いていきたいと思う。
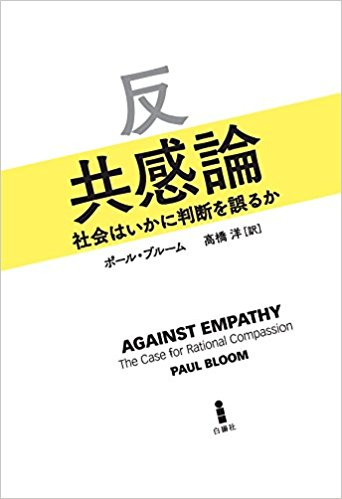

最近のコメント